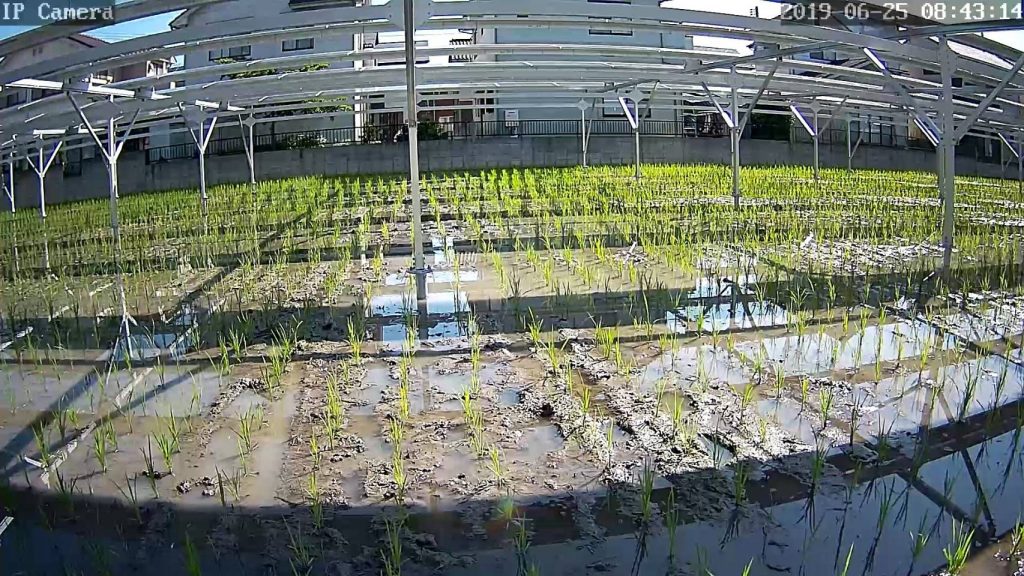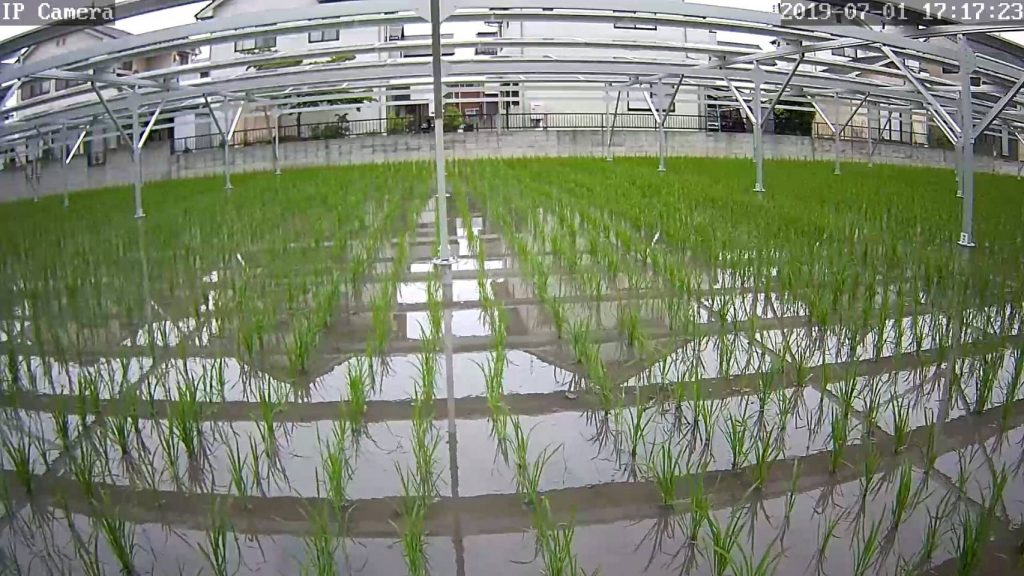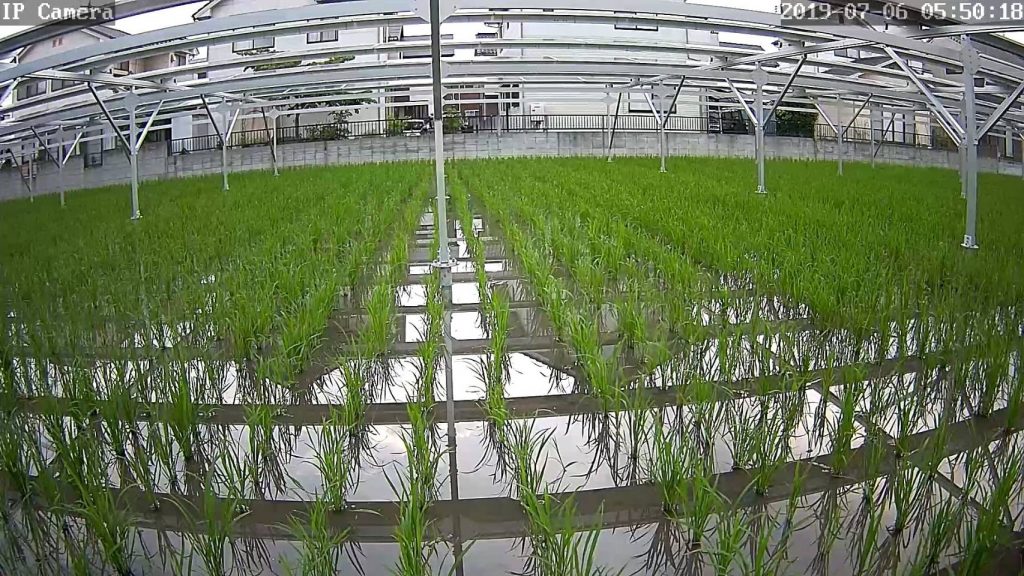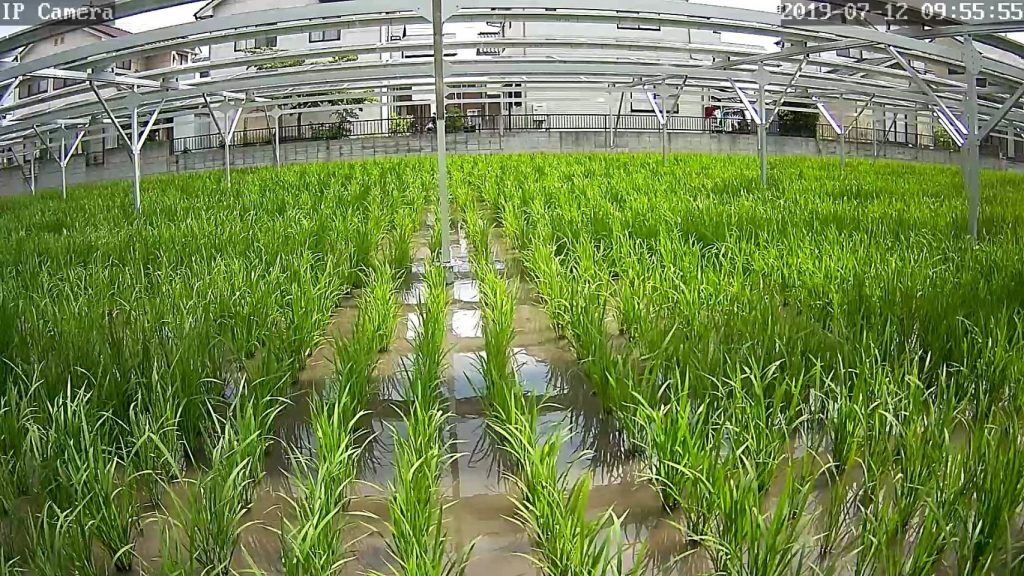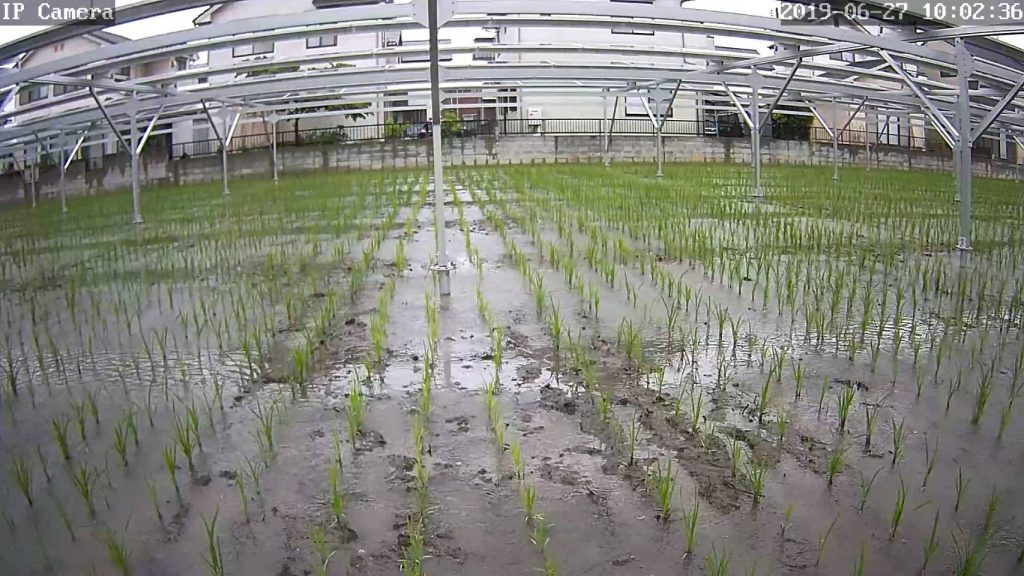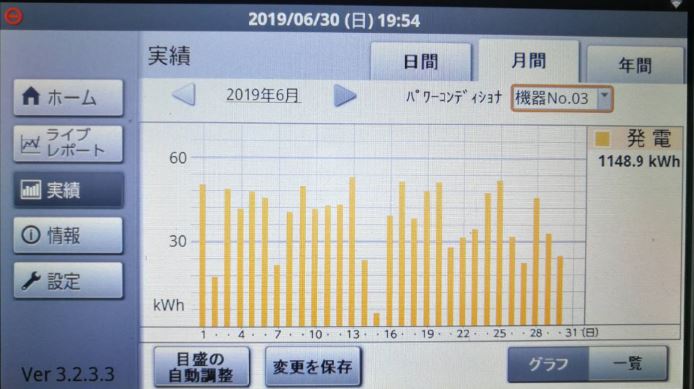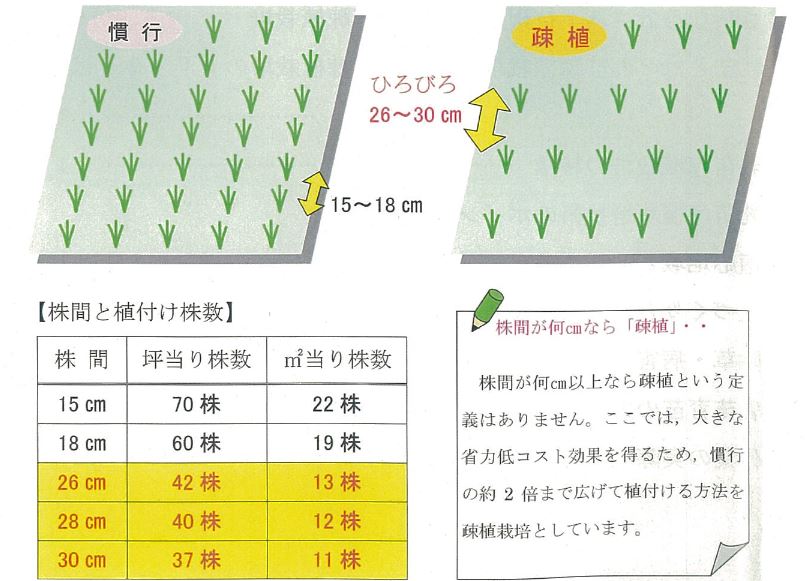ねこGです。
井戸水の用途ですが当面栽培水、洗浄水、保温水用途を想定しています。水温は10m掘れば年中一定、5mでも大体一定らしいです。また、水量についてはどんどん湧き出るようなものではなく、砂または砂利層から水を搾り取るようなイメージだと思います。5L/分の流量は蛇口をちょっと開いた程度です(参照データ ) 。三日ほど穴掘りをやってみてた結果、ここはもともと干拓地(高梁川の下流域)ですのでほとんど粘土と細かい砂でした。従って、塩ビパイプに水を流し込み土を水流とともに地上に流しだすだけで約8m掘れました(参考水圧法)。途中5m位の所に少し砂が多い所があったようです。
井戸掘り現場から100mくらい離れたところでグーループホーム建設のため地盤調査をやってもらっていたことを思い出しだしました。20mまでのボーリング結果です。これを参考にすると理想的な井戸は15mほど掘る必要があるようです(赤丸)。がんばれば掘れないことはないと思いますが、ちょっと自力ではしんどい深さです。このあたりの地下水位はたぶん1m弱ですから△のところ(5m弱または7m位)から搾り取れば なんとか 浅井戸にはなりそうです。他の人がどれくらいの深さ掘っているかのデータがあります。たいていの人は5-6m前後です。
今回打ち込んだ塩ビパイプの先端部には3mmの穴を多数開け取水孔にましたが、砂が細かいのでたぶん大きすぎます。1mm位の穴にしないといけないと思います。掘り方はわかったので7mを目安に再度掘りなおします。 1mm位の穴 をたくさん開け水量を少しでも多くしたいです。まずは費用をかけずに浅井戸を作ってみたいと思います。
| 井戸水の用途 | 水量(L/分) | 課題点 |
| 水耕栽培の水 | 小 5 | 塩分濃度 |
| 育てた野菜の洗浄水 | 中 10 | 雑菌 |
| 冬場の保温水 | 大 20 | 流量 |

 現場から100mのところのボーリング結果。
現場から100mのところのボーリング結果。